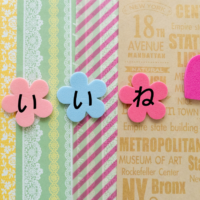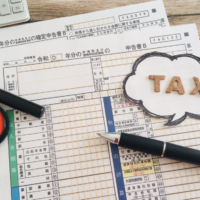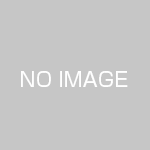今回は久々にリスクマネジメントについて書きたいと思います。
自分たちには関係ない・・と思っていても、危機は突然訪れます。危機発生時、適切な対応をするためには普段からの準備をしておくことが重要です。
昨年の5月に「危機発生時の記者会見の開き方(前編)」「危機発生時の記者会見の開き方(後編)」という記事をアップしましたが、お読みいただけたでしょうか?
記者会見の開き方や進行の方法がわかったとしても、自分が実際に経験していなければ、記者の前に立つと緊張しますし、発言がしどろもどろになることもあるでしょう。
しかし、あらかじめ記者に聞かれる質問の傾向がある程度わかっていれば、緊張の度合いも下がってくると思います。
そこで、今回は危機発生時の記者会見において記者から聞かれることが多い項目をご紹介します。
状況の確認
まず聞かれるのが「事件・事故発生時から現在までの状況の確認」です。
ただ、会見の冒頭で現状等の説明について不足なく説明している場合には質問されないこともあります。
答える際には次の点に注意しましょう。
1.5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・どうして・どのように)に従い、ゆっくりと簡潔に話します。
2.被害状況、規模、現在の状況(これらは記者に質問される前にこちらから話すようにします)
3.個人情報に関するものは公表しない。
事件・事故の原因
「なぜ、このようなことが起こったのか?」という類の質問です。
事件・事故の原因についてはその究明に時間がかかります。会見を開いた時点では判明していないことも多いでしょう。よって「原因については現在調査中です」のような回答が多くなると思います。
しかし記者は「あぁそうですか・・・」と言って、簡単には引き下がってはくれず、違う角度から質問を投げかけてきます。
ここで注意すべきは次の項目です。
1.会社としてどのように回答するか決めておく(「現在調査中」「警察が調査中ですので現段階ではお話できません」等)
2.憶測で話さない
3.会社として原因究明に真摯に取り組んでいるという姿勢を終始一貫させる
4.記者の執拗な追求があっても、会社として決めた回答の路線(「現在調査中です」)を維持する。ただこのとき記者の質問に対し「現在調査中です」を繰り返すと「バカにしているのか」と取られ、誠意が感じられないので印象が悪くなります。類似の回答パターンを持っておくとよいでしょう。
例:「憶測でお話することはできない」「仮定のお話はできません」などです。
事件・事故の継続性
工場の爆発事故、火災、食中毒、個人情報漏洩などによる危険性が継続しているのか否かは記者にとって大きな関心事となります。
これらの質問に回答する際には「事件・事故の原因」と同様に憶測・仮定で回答しないことが大切です。
また、事件・事故の影響を最小限に食い止めるように最大限努力をしているという姿勢を見せることも重要です。たまに他人事のように記者の質問に答えている記者会見を見ます。決してこのような口調、態度をとってはいけません。そういった口調や態度は、記者やその映像を観た人の心象を悪くし、SNSに悪評や批判のコメントが溢れ収集がつかなくなることもあります。
対策方法
事件・事故への具体的な対応策です。
応急的にどのような処置を講じ、被害の再拡大を最小限に食い止める努力をしたのか?その後の本格的な対応はどのようなものだったのか?について、順を追って簡潔にまとめて話しましょう。
ここで注意しなくてはいけないことは、最初にとった応急措置に対し「措置が的はずれではないのか」「もっと良い方法があったのではないか?」「なぜその方法を選んだのか?」と記者に問い詰められ、しどろもどろになったり、明らかに逃げていると取られかねない回答をしてしまうことです。
緊急時の場合、最初の一手を間違うことは十分に考えられます。もし、冷静に考えて最善の方法とは言えない方法をとったのであれば、それは正直に言うべきでしょう。嘘をついたりしてそのことが後で発覚した場合には会社のイメージに大きな傷が付いてしまいます。
今後のことについて
大きな火災、個人情報漏洩のような事件の場合、問題がどこまで拡大するのか予想が難しく、今後の具体的な対処の道筋を回答できないことも多々あり、曖昧な回答になることもあるでしょう。
しかし、事件・事故によっては、曖昧な回答が更に会社への批判を増長させてしまう場合があります。例えば工場の大きな火災の場合、近隣住民の避難生活がいつまで続くのか?個人情報漏洩でその中にクレジットカードの情報も含まれている場合、どのようにその拡散を防ぐのか?などの場合です。
できるだけ明確な回答をするよう心がけ、真摯な態度で一生懸命に取り組んでいる姿勢を見せることが重要です。
責任所在
「事件・事故が起きたその責任は誰にあるのか?」ということです。これについては回答が難しいことも多くあると思います。特に社員個人のミスにより起きた場合は、その人に与える影響も考慮しなくてはいけません。会見を開いた時点で、責任の所在に関する会社の方針が決定していない場合は 「現在調査中です」という回答になるのも致し方ないかもしれません。
補償について
被害者の方にどのような補償をするのか?ということを聞かれます。 これに関しては、記者に直接回答することは控えるべきでしょう。
あくまで「会社と被害者の方との間で話し合いし、決定する」という方向性を貫くべきです。しかし、ここで十分に注意するべきことは、「被害者の方の不安・痛みにより沿った丁寧で思いやりのある回答をする」ということです。
補償の発言内容について、「素っ気ない」「冷たい」と被害者の方に感じ取られると不満は一気に大きくなります。
社長はどこにいて何をしているのか?
事件・事故の大きさにもよりますが、比較的大きな事件・事故であれば「社長は今どこにいて何をしているのか?」という質問をされる確率は高くなります。
部長、役員クラスが会見に臨んでも「なぜ社長が出てこない?」「社長が説明責任を果たすべきなのではないのか?」と詰め寄られることも多くあります。
しかし、会社の方針として初期の会見時は、部長、役員クラスが会見を行うと決めているのであれば、それを通さなくてはいけません。また、「今回のことについて社長はどのように言っているのか?」と聞かれることもあるので、危機時の広報マニュアル等で社長の発言について準備しておくほうがいいでしょう。
以上が危機発生時の記者会見で質問される確率が高い項目でした。
いかがでしたでしょうか?
客観的にこれらの項目を俯瞰すると「まぁ、そうだろうな」「よくテレビで観る会見でも同じようなことを聞かれているな」と感じるでしょう。
しかし、普段からこれらの項目について準備し、できるだけ危機毎のケースで模擬会見を経験しておかないとスムーズにこなすことは至難の業です。
消防訓練、防災訓練と同じようなことですね。
危機発生時の記者会見次第では会社が存続できなくなることもあるので、広報担当者の方はこのことを普段から意識しておくことが大事です。
本日の記事は以上となります。
ありがとうございました。